昨年の12月に私の妻は会社を退職し、私が今年の1月から正社員として転職をしたので、私の扶養に入る計画を夫婦で話し合っていました。
しかし健康保険の扶養に関しては、退職日の翌日には直ぐに扶養として加入出来る事が分かりました。
世の中には知らないと損をしてしまう話が沢山ありますので、なるべく新しく行おうとしている事は、事前にしっかりリサーチする事が大切だとつくづく思わされました。

「健康保険の扶養」と「税金の扶養は」別枠である。
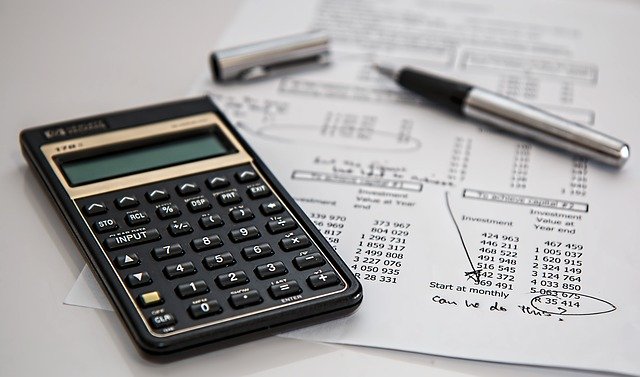
私の妻は年末の12月がたまたま退職月だったので、結果的には良かったのですが、人によっては年内の途中に退職する方もいるかと思います。
ここでは年内で既に扶養条件の年収130万円以上を稼いでいたからと言って、扶養そのものに入る資格が失われる訳では無いと言うことを知る必要があります。
ですので退職後に働く予定も無く、無職無収入であれば「健康保険の扶養」には加入する事が出来ます。
年内に130万以上稼いでいたからと言って、夫の扶養の恩恵を受けずに「国民健康保険」で年内を乗り切るのは実はとても損をしているのです。
私もこの記事を読むまでは知らなかった為、扶養自体は両方とも同時に入らなければならないと思い込んでいました。
無職無収入であれば「健康保険の扶養」に入れる。

どうやら退職日以降に無職無収入であり働いていなければ、それは将来に向かって年間の収入が130万円未満と判断されるので、原則は退職日の翌日から直ぐに「健康保険の扶養」に入れるのです。
逆に年内の最後だからと言って、11月にパートなどで一月15万円稼いだりしてしまうと年収180万円(15万×12カ月)の見込みが立ってしまうので、パートとして働き出した月から扶養から外れないといけないと言う仕組みになっているのです。
その年はパートで30万円しか実際の年収が無かったとしても、月の稼ぎを12ヶ月掛けることで将来の年収見込みの計算がなされるようなのです。
今回の私達のパターンでは妻が退職月の翌月から扶養に加入する予定だったと言う事と、妻が退職後に特に「健康保険」を使うような用事が無かったので、取り合えずは問題無く扶養に移行する事が出来そうなので良かったです。
この事を知らずに何ヶ月も「健康保険の扶養」に入らずに退職後に「国民健康保険」で病院の診察などを受けていたら、本来優遇されるはずなのに無駄に保険料を多く支払う事になってしまうのです。
「健康保険の扶養」と「国民年金第3号被保険者」は原則同じ!


「健康保険の扶養」と同様に「年金の扶養」にも入る事が出来るので、もし知らなければ退職後に何ヶ月もの間も国民年金の支払いをしなければならないのです。
夫の扶養に入れば、健康保険と年金の負担額は実質無料になるのでコストパフォーマンスとしてはかなり高いです。
扶養に入ったからと言って夫の社会保険料の金額が上がる訳でも無いので、クレジットカードの付帯サービスみたいなものと考えていいかもしれません(笑)
しかし「年金の扶養」で払った事にしてもらえるのは国民年金保険料だけであるので、老後に受給できるのは国民年金からの老齢基礎年金だけになります。
ですので足りない分は個人型確定拠出年金(iDeCo)などに自分で加入して老後のプランを作り直す必要も出てきます。
iDeCoに関しては現段階では私も加入を考えていません。
それは不動産投資の方に資金を優先したい為、敢えてiDecoは使わない決断をしました。
iDecoは原則60歳までは引き出す事が出来ないそうなので、いくら節税出来るとは言え、資金が老後まで拘束されている状態であると私は判断しました。
あまり詳細を知らない為、iDecoに関しては割愛させて頂きますが、やはり興味ある方もいると思いますので、一応詳細を下に貼っておきます。
結論:扶養の仕組みを知り、働き方を柔軟に変えていこう!

このように何も知らずにただ闇雲に働いていても、無駄に税金を多く払う事になってしまうこともあるので、敢えて働き過ぎないと言う選択も必要になってくるのです。
世の中の仕組みは、ただがむしゃらに働けば働いた分だけお金が残る仕組みでも無いので、しっかりと社会システムを理解した上で行動していかなければ損をしてしまいます。
私も全てを知っている訳では無いので、新しい物事が目の前に来たら、基本その都度調べてから最善の行動を取るように心掛けています。
それでも失敗することもありますし、だからと言ってめげずに教訓にすることで次回同じような状況が目の前に来たとしても、その経験が役に立ってくれるものです。
今はグーグル先生(インターネット検索エンジン)に聞けば何でも分かるような時代であるので、とても有難い時代になったものです。
ネットを辞書代わりに上手く有効活用して、何とか老後まで生き抜いていきましょう。



コメント